人形遣い、義太夫、三味線が三業一体となった時、文楽という世界に比類なき舞台芸術が華開く。親が子を思い、子が親を思う。男が女を、女が男を求めるとき、そこに渦巻く人間絵巻の数々が、時代や世代を超え普遍的な“人間の情"として、竃、づいている。それは、近松門左衛門が道頓堀界隈を歩いたであろうその時から、はや300年余りの歴史を紡いできた。改めて、近松の筆の力に感嘆すると共に、その床本を囲んでどう舞台に物語を華咲かそうかと、目を輝かせ思考錯誤した竹本義太夫や三味線弾き、人形遣い等の歴代の芸人やその舞台を愛して止まなかった多くの人々の思いが今も舞台に生きている。
私達は1月6目に文楽を鑑賞後、人問国宝で七代鶴澤寛治氏の三味線とお話をまじかに拝聴する機会を得た。
今回の講座では、人問国宝を囲むとあって、参加者は皆緊張感で固まっていた。しかし、講義が始まると、鶴澤寛治氏の三味線の音色とその大きさに包みこまれ、やがてなんとも言えない安堵感さえ味わえたのは、その人となりのなせる技だろうか。
このような貴重なお話の一部始終を40名余りだけのものではなく、読者の皆さんにもお裾分けしたく筆をとった次第だが、目の前で弾いていただいた三味線の音は文章では表現し尽くせない。神髄のその音色は私の拙い文章ではなく、文楽劇場に足を運び、自らの耳で、是非、是非、鑑賞いただくことをお奨めしたい。そして、このような素晴らしい舞台芸術が大阪で開花し、育まれていることを、誇りとして語り伝えていただきたい。又、鑑賞する機会があれば、文楽を支える人々の思いや日頃の切硅琢磨しながらの修業で裏打ちされているのだと思いを馳せてみて欲しい。そして、その舞台が過去より伝えられ未来に伝えられていく一場面を鑑賞しているのだという思いで眺めると、大河の流れに命をゆだねるよ一うな広大な開放感に浸ることができる。
七代鶴澤寛治氏の好きな言葉は、『恩』。恩を恩だと思える心掛ける事。人が生きていくということは、様々な『恩』のお蔭でもある。そして、人は様々な関わりの中で、命を長らえている。それは、周囲にいる人、杜会を支えている人だけではなく、今は亡き歴代の人々の智恵やら思いやらにも行き当るし、更に広げれぱ『神恩』とも言える、万物の恩にも包まれている。義太夫三味線として人間国宝に辿りつき、鶴沢寛治という名人の域まで達し得たのは、様々な『恩』に感謝し、精進されてきた賜物だろう。そして、私たちも、目々の生活の中で、『恩』を『恩』だと思える心掛けを見失わないようにしたいものだ。
また、今回の舞台では、人間国宝という大木の足元で、芽吹いた若葉、お孫さんの鶴沢寛太郎君、今年13才の初舞台も見所だった。背後に祖父の三味線と柔らかな視線を受けて、背筋を伸ばして琴の演奏を披露する姿に頼もしささえも感じた。文楽は、血縁での信承ではなく、実力主義なので、生まれだけは名跡は継げない。だから寛太郎君が、祖父の血と薫陶を大切に受け継ぎ修業を重ね、人間国宝に辿りつくことができるとしても、まだ50年余りの年月が必要となろう。今回同席した中でその襲名披露の席に着く事が出来るのは何人いるだろうかと見まわした時、塾生の原季美子さんに促されて初めて文楽と出会ったお孫さんの13歳の原周平君がいた。その周平君に、50年後の寛太郎君の姿を見届けて欲しいという思いを託す事にしよう。そして、もし寛太郎君の晴れ姿を目にする日があれぱ、21世紀の初めに、祖母と共に寛太郎君の初舞台を目にし、七代寛治氏の襲名披露の舞台を鑑賞したことをも思い出してほしい。
伝承文化とは、そのような息の長い、深いものなのだという思いを新たにした。そして、このような積み重ねを経て、私たちは今でも、近松や文楽を支えてきた人々と、その舞台で出会えるのである。
(記:原田彰子)
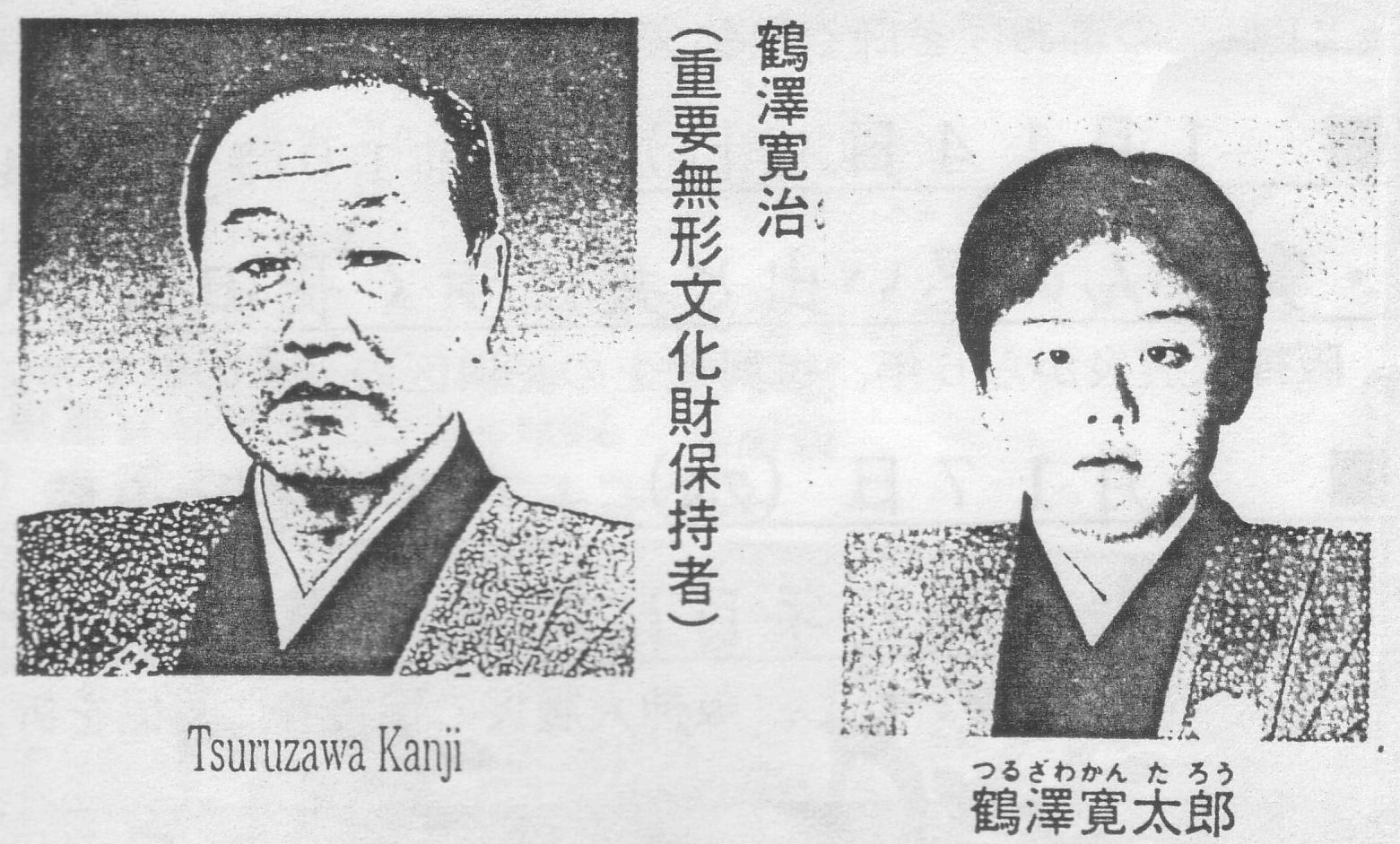
右上へ →
義太夫・三味線・人形と
三業が一体となる文楽
先ず三味線についてでございますが、琉球に輸入された中国の三弦が、琉球で蛇線になり、蛇線が永禄年間(1553〜70)に大阪の堺に伝えらました。日本には大きな蛇がおりませんので、猫の皮を張ったのが三味線の初めやと聞いております。三味線は長唄に細悼、地歌、常磐津に中樟、義太夫節・浪花節には太悼が使われ、津軽三味線も太樟ですが、義太夫三味線とは異なり擾の厚さが薄いものを使用しますので音色が変わってまいります。
三味線は、はじめ演劇用としてではなく、もっぱら仏教の辻説法で話しの流れに合いの手を入れるような簡単な伴奏用として使われておりました。それが、「浄瑠璃語り」と呼ぱれた、浄瑠璃光菩薩に祈願して生まれた「浄瑠璃姫」と源義経との恋物語を語って歩いた旅芸人の伴奏として三味線が使われるようになり、更に人形まわしが結ぴついたのが17世紀初頭でした。
17世紀中期には大道芸から町に定住し、人惰浄瑠璃として成長してまいります。17世紀の終わりの元禄時代には、近松左衛門が市井の出来事を描いた「世話物」の代表作噌根崎心中」「心中天網島」「冥土の飛脚」など文学性の高い台本書き上げ、それを見事に演じた義太夫節の生みの親、竹本義太夫に、その伴奏をつとめた竹澤権右衛門が登場して、全盛期を迎えます。
文楽人形は近松の頃は、裾に手を入れて一人遣いでしたが、後に三人遣いという形になってきました。世界的にも、三人遣いの人形芝居は他にないということで、人間以上に人問らしい動きを表現できます。その人形に義太夫の語り、更に三味線と、物語を更に劇的に楽しんでいただけるよう三業一体となって物語りが進行していくわけでございます。
祖父の浄瑠璃好きが昂じて
父が三味線弾きに
竹澤権右衛門のお弟子さんが、鶴澤や野澤、豊澤という流派を作り、各地で公演しておりました。やがて、大正末期になり、松竹株式会杜の提言により、彦六座、竹本座、豊竹座などを統合して『文楽座』となりました。
私の親父は京都の竹沢に入りまして、現在の京都座の辺りで『竹豊座』という一座を組んで活動しておりましたが衰退傾向で、おまけに文楽座に統合するおりに入っておりませんでした。このままでは活動しにくくなると考えた父は越路大夫に相談し、私は鶴澤寛治郎という方の所に預かり弟子として竹澤家から入門させたいただくことになりました。その鶴澤寛治郎が亡くなれた時の遺言で、父が鶴澤家に入るようなりましたので、私は竹澤家を継ぐように考えておりましたが、今回図らずも皆様のお薦めにより、鶴澤家に入いることになりました。私は竹澤家を離れましたが、鶴澤家、竹澤家には他にも後継者がおりますが、花澤家は絶えてしまいましたし、豊沢家も冨助君一人が頑張っていたところに龍幸君が加わったような状態で、後継者閥題は頭の痛いところ、困った事だと感じております。
私が入門いたしました戦前でも全国で何百人という三味線引きが居て、銭湯の湯船の申でも浄瑠璃を語っていた人がいたぐらいで、日常生活の風景の一部にもなっておりました。私の家は代々三味線引きではございませんで、祖父は京都で煙管屋を営なんでおりましたが、仕事は番頭に任せて浄揖璃を見て歩くのを何よりもの楽しみにしておりました。そこでr息子を三味線引きにしたら、わしが語れるやないかと」いうことになり・親父が三味線引きになったということでございます。
本日も舞台で口上を言うてくれました住大夫君の養父と親父とは京都の粟田の同じ小学校に通っておりました。当時汽車賃が高うございましたので、京都の伏見から船に乗って大阪にきて入門したとかで、住大夫君ともども親子二代にわたって竹馬の友として文楽の世界で・生きてきた仲でございます。
| 『文楽について』のページに戻る |