船場というは、京都のように千年の歴史があるわけではありません。1583年に秀吉が、信長が攻めた一向宗の石山本願寺の跡に大阪城を作りました。信長は非常に魅力的な武将でしたが、一番大切な徳を欠いていたために、光秀に本能寺でやられ、その後を秀吉が安土城下の楽市楽座に習い、規模の大きな市(いち)を大阪につくったのが発祥です。たかだか四百数十年の歴史しかありません。秀吉が在城したのは、意外に短く、15年ほどです。その後、淀君と秀頼15年くらいで、合わせて30年位を豊臣家が治め、その後260年、徳川天下であります。大阪商人は、狸爺の徳川家康が大嫌いで、秀吉贔屓ですから、太閤さんの創った町が大阪だといっていますが、大阪夏の陣で大阪城が落城した後、現在の大阪の町の大半が松平定明という家康の外孫の青年武将が、大阪の街創りをやり変えているので、徳川の作った町でもあります。秀吉は、大阪の上町大地からずっと、住吉大杜、堺までを町で繋ぐという構想を持っていました。ところが、朝鮮征伐などに手を出した上に、秀頼をたのむと言って亡くなりなり、秀吉構想は頓挫してしまいました。徳川構想は、堀川を町の縦横に巡らせ、堀川を掘った土砂を利用して大阪湾を埋め立て、海に向って干拓を進めていきました。
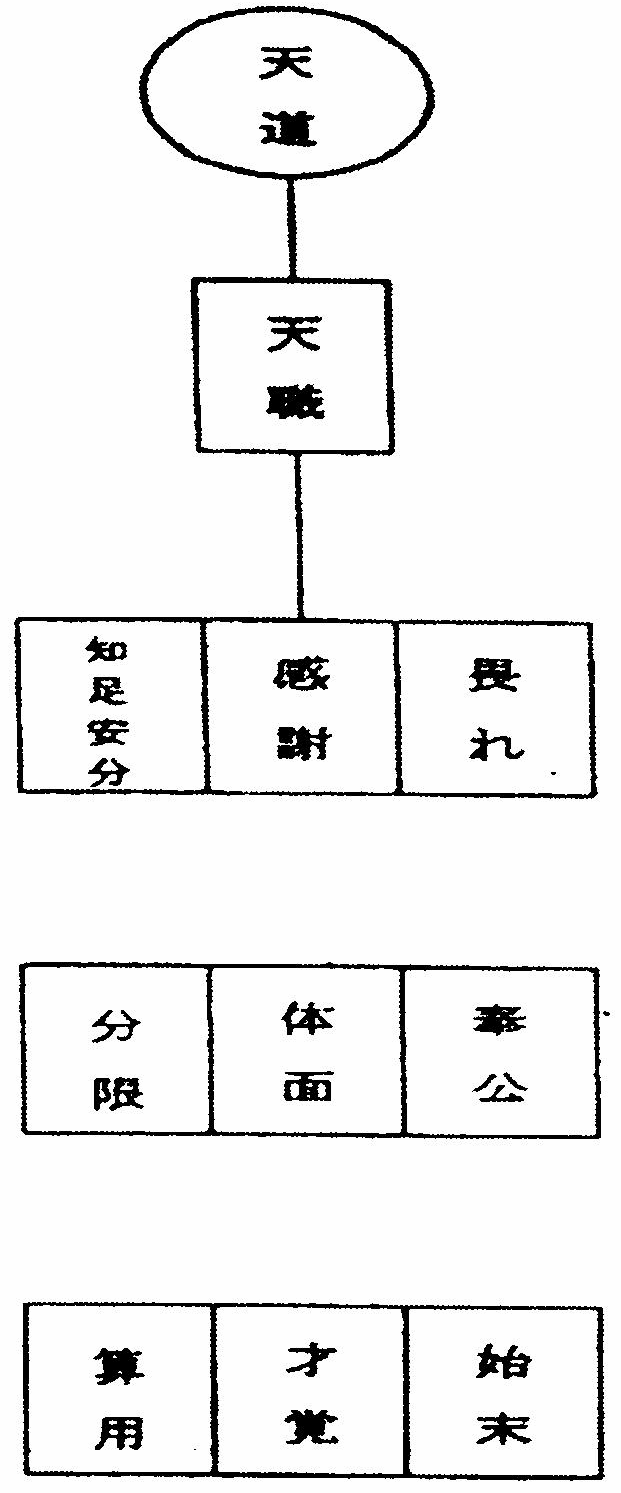 船場商法の構成図をご覧いただくと、私は40年間船場で生活しまして、船場の祖父や古老、特に私は創業者が好きだったものですから、私よりもはるかに年配の方々の話を聞いて、船場商法と何だろうと、私なりに作ったのが、この構成図です。
船場商法の構成図をご覧いただくと、私は40年間船場で生活しまして、船場の祖父や古老、特に私は創業者が好きだったものですから、私よりもはるかに年配の方々の話を聞いて、船場商法と何だろうと、私なりに作ったのが、この構成図です。一番下の始末・才覚・算用は、皆様がいつもお聞きになっている大阪商法の三つのキーワードであります。目本永代蔵という小説を書き元禄時代に活躍した井原西鶴が大阪商法とは一番下の始末・才覚・算用であると言っております。
始末とは、本来の言葉の意味は始めと終わりをきちんとするという計画性で、計画性を持ってやれば、思いつきでやるよりもはるかに無駄が少なく倹約になります。
才覚というのが、難物でありまして、戦後の目本の経済はどちらかと言いますと、アメリカやヨーロッパ等の先進国からいろんなことを学んで、模倣し経済大国になった。どちらかと言うと、人様の成功例を上手く活躍するのが、戦後の目本の才覚であります。しかし、戦前の才覚は、まったく逆で、人の真似をしないというのが、才覚でした。
人の真似をしないで、どうして成功するか。自分で編み出す。これからの21世紀は、本家返りといいますか、携帯電話の活用法は、日本が編み出した例だと思いますが、もう一度目本が目本独自の創造的な物を編み出さないと、IT革命の時代、新しい時代に生き残れない。人真似はしない。
東京通信工業という会杜からソニーに社名変更した年が昭和33年で、当時、大阪ではソニーは松下のモルモットだと言われていた時代でした。ソニーがテープレコーダーなどを開発すると、すかさず松下が大量生産して低価格で大量に売るので、口の悪い人は「あれは、松下電器とちゃう。真似下電器や」と言っておりました。戦後は、人の真似をするのは決して恥べきことでもないし、非難されるべきことでもなかった。その為に右肩上りの経済成長を成し遂げた訳ですから、しかし、戦前は人様の開発したアイデアには手を触れない、尊重し、自分は自分で独自の商法を編み出すという才覚でした。
戦後は、横並び才覚で成長してきましたが、銀行をはじめ今横並び企業は俄かに潰れてきております。大阪大学の宮本又次先生は、才覚のもう一面は、積極的に商機、商いのチャンスをつかむのも才覚だとおっしゃっています。せっかくいいアイデアを編み出しても、それを商売に繋げなけれぱ、何の成果も生まれない。だから積極果敢にやれというのが、京都商法との違いであります。京都商法とは、室町は着物、西陣は帯と、祖先からずっと続いてきたものを守り、町屋の様に細長い商売を続けていくことにあります。
ところが、太閤さんの膝元の船場商法での、才覚は、人がやらないことに挑戦することによって、成功も大きいけれど、大きなリスクもあります。新しいことを手掛け、みんながみんな成功するわけではない、だから、なかなか続かない。続かないから、何とかして永続させようと才覚をはたらかせ、のれんを降ろさないように努力するわけです。
右上へ →
算用とは、算盤に合うということですから、せっかくいい計画を立てても、黒字に繋がらなければ何の意味もない。だから、商法として算盤に合う、採算が見込まれるというものでなければなりません。この三つを先ず組み合わせることによって、時間の経過によって、信用というものが生まれるわけです。銀行の応接室などにはこの三つの横に、信用という言葉が額に入れてありますが、この三つと信用とは本質的には違う。三つの結果が、信用になっていくわけです
奉公・体面・分限がのれん永続のキーワード
その上に奉公、体面、分限とありますが、これは享保時代に生まれた商人の意識と言った方がいいと思います。
奉公とは、丁稚奉公の奉公ではなく、奉公の公は、公儀とは幕府、幕府の掟を守るという意味です。
商人とは、いくらお金を持っていると言っても好き勝手に商売をし走ら、必ず潰れる。ルールを守るという事です。奉公という概念が生まれたのは、船場の初期商人で、政商・淀屋は、豊臣家や徳川家など、時の権力者と結びついて有利な利権を手に入れました。
その利権に、中之島の干拓があり、その成功によって現在の淀屋橋のミズノビルや住友銀行の本店辺りに二万坪の屋敷を構え、その前で米相場が立ちました。個人が玄関先に掛けた橋が淀屋橋でした。淀屋が干柘した中之島に諸藩の蔵屋敷がずらっと並び、天下の台所として、天下の財の七割が流れこんできました。
江戸時代が北前船で、日本海の特産物、山形の紅花や、北海道の昆布などの全国の名産が、下関を経て、瀬戸内海を通って、大阪に荷揚げされ、そのうちの八割程度が加工され、また全国に商品が流れていきました。その中心として全盛を誇っていた淀屋が五代目の辰五郎の時に、幕府によって突然に取り潰されてしまいます。当時慕府は八十万両の金を淀屋から借りていました。殆どの藩は、淀屋から借金をして、藩の財政を賄っていました。高松藩とか、松山藩とか、参勤交代で江戸に行く途中、淀屋の屋敷の前を通る時には殿様が籠から降りて歩いて通ったという権勢を誇っていました。当時は、士農工商という身分制度で、商は儒教の一派の朱子学では、左の物を右に動かすだけで利益を得ているといるので、一番低い身分であるとしていました。しかし、天下の台所、天下の経済を動かしていたのは紛れもなく商人の金であります。淀屋が幕府に取り潰されたのを見て、何をしても儲ければいいというものではないと、奉公という意識が生まれた。つまり、ルールを守らなければ、長続きはしないということであります。
体面とは、身分社会で最も低い商人でも、商人としての誇りを捨ててはいけないというのが、体面であります。その誇りを、形にしたものがのれんであります。のれんというのは、商人の顔であります。だから、顔を汚さないということになります。
のれんというのは、もともと日本にあったものではなく、鎌倉時代に新しい仏教・禅宗が、宋から入ってきました。禅宗とは、ひたすら座禅を組んで仏に近づくというもので、その座禅を組む所が、禅堂という所で、早朝の座禅を組む時に扉を開け、深夜の座禅を組み終わった時に扉を締めるというルールがあります。その間に開閉はしません。
今日の様に天候の良い時はいいのですが、一日中扉を開けたままだと寒気暑気が入ってくるので、それを防ぐために、禅堂の入口に布をぶら下げた、これがノウレンといい、それが商家に入って暖簾と謂われるようになりました。商家の暖簾には屋号と扱う商品が染められています。暖簾を汚さないということは、信用を汚さない、暖簾は信用ということになります。あそこは暖簾が古いと。いうと、信用がそれだけ厚いということになります。暖簾が新しいというと、新店や、まだ信用がついてないということになります。特に両替商の暖簾というのは、繊維問屋の暖簾と材質が違う。繊維問屋は厚手の綿布を使いますが、両替商は麻を使いました。麻は木綿よりも強く、長持ちをします。その強い麻布が風雪でほころぴても、架け替えないので、「麻の暖簾の乞食継ぎ」といわれ、繕って古いままの暖簾を掛けていました。暖簾が古いほど、それだけの信用がありました。戦前は、創業何代目だという暖簾の古さがステイタスでしたが、戦後は大企業、中小企業、零細企業という区分けになり、歴史ではなく大きさで評価されるようになったのです。
分限とは、身の程という意味で、企業にしても、個人にしても、器量というものがあります。「あの人は器が大きい」というと大きな人物、「あの人は器が小さいなア」というと小さな人物だと軽視した表現になります。同様に、企業にも器があり、その器を忘れたら長続きしません。このコップが私の器だとすると、この器の量しか水が入らない。器以上に水を入れると、こぼれてしまう。ですから、自分で自分の器の大きさを認識をするかということで、それによって永続がかなうかかなわないかということになります。
バブノレ時代は、この分限を忘れていた。「身の程を知って商う腹八分」という言葉がありますが、当時は腹十二分に食い過ぎたために、お腹をこわし、今その後遺症で苦しんでいるわけであります。ただ、自分がどれだけの器なのかということが、なかなか分らない。祖父は八掛けの八掛けと言っておりました。「和田哲が百の力があるとすれぱ、文句なしに八十。それでも足らん。もう一度八掛けしなはれ、六十四だす。百だと思ったら、その実六十四しかないということを胆に銘じておけば、万が一潰れることがおまへん」ということです。